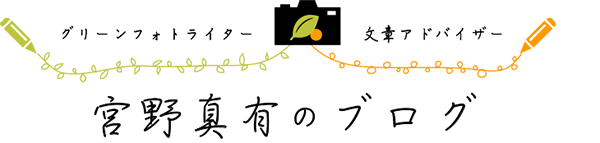植物なるほど001:読めなくても覚えなくてもOK! 学名は世界の共通語。
せっかく勉強したので、植物や自然が好きな方にちょっとうれしい(かもしれない)豆知識を、少しずつお届けしていきます。

夏の高木の梢 2015.8.15 東京都文京区
図鑑などで、植物の名前や動物の名前に併記してある「学名」。
これってなんでしょう?
実は、理解しておくととっても便利な、世界の共通語。
読める必要も覚える必要もなし! 結構、素人の役に立ってくれます。
学名って何?

学名って、たとえばこんなものです。
和名:ヒガンバナ、マンジュシャゲ 英名:red spider lily 学名:Lycoris radiata
和名:ムクゲ 中国名:木槿(ムーチン) 韓国名:무궁화(無窮花、ムグンファ) 学名:Hibiscus syriacus
和名:ライオンゴロシ 英名:Devil’s claw 学名:Harpagophytum procumbens
図鑑には必ず、Wikipediaなどにも基本的に、学名が記載されています。
学名の便利な使い方
学名で画像検索をかける
学名をコピペしてWebで検索をかけると、関連の画像、文字情報(海外のものを含む)が、ずらっと出てきて、一覧することができます。
たとえば、先日の記事で紹介した奇妙な植物「ライオンゴロシ」、学名:Harpagophytum procumbens。私が見たのは乾燥した実ですが、では、アフリカで生えている植物の全体は、どんな姿をしているのか?
学名の「Harpagophytum procumbens」で画像検索をかけると、現地で花や葉をつけた状態の生きている姿の写真を見ることができます。
「Harpagophytum procumbens」で画像検索してみると……
学名でWeb検索をかける

変わった植物も、通常のWeb検索で学名で検索をかければ、Wikipediaの記事などがヒットします。
もちろん和名で検索をかけてもいいのですが、和名は漢字表記かカナ表記かなど、表記のゆれがあります。また、通称や流通名だと、ヒットしにくいこともあります。
海外の植物は説明の詳しい英語などのサイトがヒットすることもあります。読むのに語学力が必要ですが。
海外の記事中の写真の動植物名がわかる

海外のネット記事で、魅力的な植物や動物の写真に学名が表記されていたら、外国語が読めなくても、学名を検索するだけで、なんという生物の話題なのかが理解できます。
またムクゲのように、植物の名前は基本的に分布している国ごとに違います。名前が違っても学名を見比べれば、同じ植物のことをいっていることがわかったりもします。
園芸種の流通名にも使用されている

お花屋さんで売っている、カタカナの多い覚えにくい植物の名は、学名の属種名そのものであることも結構あります。
《例》
トルコキキョウ→ユーストマ(学名:Eustoma grandiflorum)
ヒガンバナ→リコリス(学名:Lycoris radiata)
ドラセナ・コンシンナ(Dracaena concinna)→学名ママ
ドラセナ・サンデリアーナ(Dracaena sanderiana)→学名ママ
そういうものだと理解すれば、覚えやすくなる、かも?
知るとわかりやすい! 学名のお約束
さて、こんなふうに便利な学名には、いくつかの約束があります。頭に入れておくと便利です。
学名は、ひとつの種にひとつの学名
種に固有の名前で、海外でも共通です。どこの国の図鑑を見ても、同じ種には同じ学名が記載されています。
学名はふたつの単語でワンセット

学名は、日本の人名の姓・名のように、ふたつの単語の組み合わせからできています(二命名法/二名法)。
前半が、分類上の「属」を表し、後半が「種」を表します。
《例》
ムクゲ→学名:Hibiscus syriacus
フヨウ→学名:Hibiscus mutabilis
(通称)ハイビスカス(ブッソウゲ、アカバナー)→学名:Hibiscus rosa-sinensis
花が似ている3つの種の花は、いずれも学名の前半が同じ「Hibiscus(ハイビスカス)」で、同じHibiscus属(アオイ科フヨウ属)の仲間だとういうことがわかります。
学名はラテン語

学名は、かつてヨーロッパの学術論文で使われていたラテン語で表記されています。
日本語がわかる人にとって、ラテン語のいいところは、ローマ字読みをすると大体読みが合っている、というところです。
《例》
Rosa chinensis(ロサ・キネンシス)原種の赤バラ
Rosa gigantea(ロサ・ギガンティア)原種の白バラ
Rosa foetida(ロサ・フェティダ)黄色いバラ
学名はたまに変わることがある
なんらかの理由で、学名が変わることがあります。最初にある学名をつけたけれど、長く調べていくうちに分類が変わった、いろんな説があって、採用する説が変わった、などの場合のようです。
学名にはデータがくっついていることもある

末尾に命名者を示す略語や、学名が発表された年など、いろいろなデータがくっついていることもあります。しかし大事なのは頭の2語。残りはオマケと考えれば、わかりやすいでしょう。
《例》
ウメ(梅)→学名:Prunus mume Sieb. et Zucc.
ハマボウ→学名:Hibiscus hamabo Sieb.et Zucc.
トサミズキ→学名:Corylopsis spicata Sieb.et Zucc.
いずれも日本の植物ですが、来日したドイツの医師・博物学者のシーボルト(Philipp Franz B.von Siebold)が、植物学者のツッカリーニ(J.G.Zuccarini)と連名で命名したため、ふたりの名前が末尾に入っています。

植物について調べ始めたころ、「学名ってなんだろうなあ。和名や英名のほうがわかりやすいのに」と思っていましたが、理解してみるとなかなか便利に使えることに気づきました。
必要なときだけでも使ってみると、植物の世界が身近に感じられますよ。
Information
東洋文庫アカデミア「文章が苦手な人のための『自分史』入門」
自分史を書くことは、自分という人間の棚卸しを行い、新たな自分を発見する作業であり、過去の歴史や過ぎ去った時代に関する学びや気づきも得られる作業です。ですが自分を客観的に見つめて文章を書くことは、ある程度文章に慣れた人でもなかなか難しいものです。この講座では、自分史を書きはじめる前に知っておきたい基礎知識について講義します。また、実際に手を動かして自分史年表を書いていただき、自分史執筆のきっかけを作ります。
- 講座詳細 http://www.toyo-bunko.or.jp/academia/lecture51005.html
- お申し込み方法 http://www.toyo-bunko.or.jp/academia/application.html
Information
2015年冬、かさこ塾祭りに出展します。
Information
「宮野真有の文章術レッスン」
あなたの思いをかたちにする文章、お手伝いします。
対面で行う個人レッスンの受講希望者を募集しています。
都内にて随時。日時と場所は、ご相談の上で決めます。
無料コースと有料コースあり。
- 最新のお知らせは、下記でご確認ください。
http://miya-mayu.com/category/lesson/ - お問い合わせは、メールフォームからどうぞ。
- お申し込みは、文章術レッスン申込用フォームからどうぞ。
宮野真有ツイッター(お気軽にフォローどうぞ。基本フォロー返しします)
https://twitter.com/miyano_mayu
宮野真有Facebookページ(「いいね!」をするとブログの更新情報がタイムラインに届きます)
https://www.facebook.com/miyanomayu