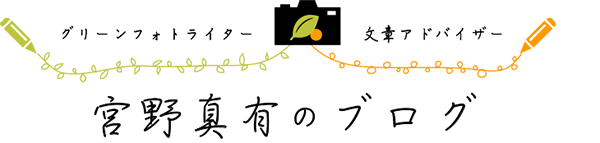〝探索の旅〟へ。中学生・高校生の「自分史」も登場の「クエストカップ2017」が刺激的。
「自分史」とは、自分と向き合うことと見つけたり。
全国の中学生・高校生の代表者が集うイベント「クエストカップ2017」を、一般参観してきました。

クエストカップ2017 2017.2.19 東京都千代田区・紀尾井ホール
クエストカップ2017とは
「宮野さん、中高校生の『自分史』で、おもしろそうなイベントがありますよ」
知人に紹介されて、今回初めて知った「クエストカップ2017」。全国の中高生によるプレゼン大会で、キーワードは「クエスト」のタイトルどおり「探究」です。
【参考】
大会概要 クエストカップ2017
全国96校約1万3千人の中高生が、1年間の成果をプレゼンテーション。実在の企業や先人を題材に答えのない課題に取り組む「クエストエデュケーション」。仲間と共に話し合い、考え抜き、生み出した探求の成果を、社会に向けて発信します。
(クエストカップ2017 大会概要より)
以下の三つの部門に分かれ、全国大会は週末土日の2日間にわたって開催されます。
- 企業とタイアップして、企業が出す課題に答える「企業プレゼンテーション」部門
- 日本経済新聞の「私の履歴書」を題材に、先人に学ぶ「人物ドキュメンタリー」部門
- 自分の過去と未来を考え、発表する「自分史」部門
私は「自分史」部門に興味を持ち、「人物ドキュメンタリー」部門と「自分史」部門の発表のある日曜日に参観しました。配分としては、「自分史」部門の発表が4名、「人物ドキュメンタリー」部門の発表が8チームと、「人物ドキュメンタリー」部門の方に時間が多くとられていました。
重視されるのは「探索」と「独自の切り口」
私は一般参観者として気軽に参加しましたが、来場者の多くは、出場する中高生とその教師、家族、そして教育関係者、協賛企業関係者だったようです。
しかしこれが、赤の他人の大人が見ても非常におもしろい。審査員も、「今年はレベルが高かった」と講評で賞賛していました。
全体に、「答えのないテーマに取り組むクエスト=探究」というテーマに従って「自分の切り口」「独自性」が重視されており、自由な空気を感じました。「こうでなければならない」「こういうのがいい」「それはダメ」といった縛りがあまりなく、自由な発想と試みが評価されている印象を受けます。
中高生のまっすぐな言葉に圧倒される「自分史」部門
「自分史」部門は、少し遅れて参加したため、全部は聞けなかったのですが、まっすぐで明晰な言葉がとてもきれいで強くて、胸を打たれました。
もちろん未熟さも粗もありますが、それにめげず、最後までやりぬき伝えようとする姿勢が、すがすがしく感じさせます。
見ているこちらが、大人だからと自然に上から見てしまう視線のいびつさを、洗い出されるような気がしました。懸命に発信して、表現しようとするパワーに圧倒されます。若いってすごい。
自分と向き合い、劣等感からも逃げず、感情的になりすぎず、淡々と伝えることのすごみに、年齢は関係ない。いや、生半可なずるい大人では、これだけの力は出せないのでは。文章もよかったのですが、声に出して語ると、パワーや魅力が伝わります。
練り上げられた「表現」が見事な「人物ドキュメンタリー」部門
私も、人前で話したり発表したりには、緊張も苦手意識もあるし、工夫や苦労をしているのですが、中高生のチームによるプレゼンは、以下のような工夫がふんだんにあって、本当に見事でした。
- シナリオづくり(意外性、独自性がある)
- 演劇(演技力高い)
- 歌(歌ってました)
- ダンス(踊ってました)
- スライド(舞台上の実演とあいまって総合芸術みたいになってた)
演劇コンテストじゃないですよ。プレゼンです。
全体に、考えついたアイデアと使える表現の全部を練り上げて、よくよく練習してのぞんだという空気がよく伝わってきました。
「ああ、表現ってこういうものだ」と感じました。はじける火花のような思いつきも大事だし、構成してまとめて力強く表現することも必要。その途中のどのひとつもおろそかにできない。
自分がやるときにはつい、できるだけ要領よく片づけようとしがちで、もちろんそれも必要なわけですが、全力でやれば結果にはあらわれるものだなと感じます。
生きることは「クエスト(探索)」だ
クエストカップは、全国大会に出て競い合うかたちになっていますが、その過程での体験、学びを重視する教育のかたちとして、非常におもしろく、価値ある試みになっていると感じます。
教育って、どうしても文部文化省的な枠組みの中で語られがちですが、それ以外の社会や大人と子どもがつながったり影響を受けたりする仕組みがもっとあってもいい。
そう感じている私には、とてもおもしろい活動に映りました。見ているこっちが、励まされたり、勇気や希望をもらえるシーンが多々ありました。
毎年開催されているそうで、興味のある方には一般参観をお勧めします。誰でもチケットを購入(無料)して、参加することができます。
【こちらもあわせてご覧ください】
宮野真有ツイッター(お気軽にフォローどうぞ)
https://twitter.com/miyano_mayu
宮野真有のブログ Facebookページ(「いいね!」をするとブログの更新情報がタイムラインに届きます)
https://www.facebook.com/miyanomayu
宮野真有の植物時間 Instagram(お気軽にフォローどうぞ)
https://www.instagram.com/miyanomayu/